

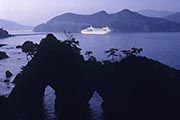
ピンカン島(ジェームズ・ボンド島)、タイ、アンダマン海
鍋釣岩、奥尻島、北海道
穴通磯、大船渡、岩手
|
連載 「海の名前」 2020年12月号 |
|
〜 海食洞門 〜
≪海蝕:海触:海食≫は波、潮流、海流など海水の動揺、海水の化学的作用、波の打ち上げによる湿気と乾燥、そして波によって動揺する岩や砂が海岸を構成する岩にぶつかり、海岸を削り地形を変化させる作用です。 |
 |
 |
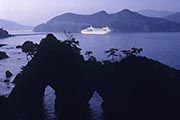 |
ピンカン島(ジェームズ・ボンド島)、タイ、アンダマン海 |
鍋釣岩、奥尻島、北海道 |
穴通磯、大船渡、岩手 |
|
|
海の写真のボルボックス © 中村庸夫 無断転載を禁止します。 |